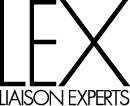アロンソ氏と日本のキツネ
2024.08.08
昨年の9月にイタリアに滞在したとき、トリノにあるエイナウディの書店に行った。エイナウディというのは、トリノで創設されたイタリアの老舗出版社で、直営の書店も経営している。別にトリノ以外でも直営店はあるのだが、ミーハーな私は、どうせならとトリノに行った機会にエイナウディの書店を訪れたのだった。そこで特にあてもなく書棚を見ていると、『アロンソ氏と日本のキツネ』(Il signor Alonso e la volpe giapponese)という本をみつけた。副題には「砂の遊びにおける治療の事例」(Un caso clinico nel gioco della sabbia)とある。手に取ってページをパラパラめくってみると、中に掲載されている写真から、「砂の遊び」というのはどうやら箱庭療法のことだということがわかった。カウンセリングを受けるクライエントが、砂の入った箱に小さなおもちゃや人形などを配置して作品をつくり、それをもとにカウンセラーがクライエントの言語化できない気持ちを読み解いていくという心理療法だ。

私が箱庭療法を知っていたのは、知り合いに薦められて最相葉月の『セラピスト』という本を読んでいたからだ。ノンフィクション作家の著者が精神科医らに取材を重ね、心の病とその治療のあり方に迫った大著だ。エイナウディ書店で見つけた『アロンソ氏』のほうは130ページほどのボリュームで、写真もふんだんに使われていて読みやすそうだ。一般的に、日本とイタリアには共通点もたくさんあるが、イタリア人と接していると、ちょっとした日常の言動をとってみても、日本と大きく感覚が違うと痛感させられる。こと心の機微を丁寧に読み取っていく心理療法には、その感覚の違いが色濃く反映されているのではないか。箱庭療法で日本とイタリアを比較すると面白いに違いない。しかも、どうやら「日本のキツネ」も出てくるらしい。この本は買って損はないだろう。
以上のミーハーな理由で、専門家でも何でもない私は『アロンソ氏と日本のキツネ』を購入したのだが、これがなかなか考えさせられる本だった。順を追って説明しよう。まずは著者について。クレメンティーナ・パヴォーニという名前の心理学者で、1948年、北イタリアのブレーシャ生まれで、ミラノ在住。イタリアの分析心理学協会でユングを学んでいた彼女は、彼が提唱した箱庭療法に興味を持ち、15年ほど前から自らが行う心理療法に取り入れているとのことだ。
さて、「日本のキツネ」登場の前に、本書の前書きの時点で私は大きな問題にぶち当たった。名称の違いだ。そもそもイタリア語で「砂の遊び」というものを日本語では「箱庭療法」と呼ぶ。もともとは在野の心理療法家ドラ・カルフがユング心理学を取り入れて現在のスタイルにしたものらしい。英語で「砂遊び療法」(Sandplay Therapy)と呼ばれていたものを日本に持ち込んだのは、なんとあの有名な心理学者の河合隼雄である。彼が助教授時代にスイスに留学した際、カルフと出会い、「砂遊び療法」を教えてもらった。ゆえに「箱庭療法」と翻訳したのは河合隼雄である。厳密に言うと、河合はドラ・カルフの「砂遊び療法」に、自の解釈を加えて日本に適応させたので、名称が直訳でないのは当然かもしれない。
さらに名称の違いでいうと、「クライエント」も曲者だ。日本の心理療法の世界では医師をセラピスト、相談者や患者をクライエントと呼ぶのが一般的だそうだ。ところがイタリアではセラピストを「分析者」(analista)、そしてクライエントを「分析中の人」(analizzante)と呼ぶ。それぞれ「患者」という表現を避けた結果なのかもしれないが、同じものを示すのに、かなりかけ離れた二語になっている気がする。本作『アロンソ氏と日本のキツネ』は、要約すると、セラピストのパヴォーニが「クライエント」のアロンソ氏に「箱庭療法」を実施した記録なのだが、このような言語的観点から、さっそく日本とイタリアの隔たりを感じずにはいられなかった。
気を取り直して読み進める。アロンソ氏が箱庭療法でつくった最初の作品は以下のようなものだ。横75センチ、縦50センチ、高さ7センチの箱のなか、右上に両親を思わせる男性と女性の人形が置かれ、その手前にU字磁石、その磁石の向いている方向に天使の小像が置かれ、さらにその天使は左下につくられた山の方角を見ている。その山の向こうには輝く玉があり、両親のいる場所からは、それが見えない。パヴォーニによると、性別を持たない天使は、自分の肉体を自分のものに感じられないアロンソ氏を表している。アロンソ氏の母親は重度のうつ病を患っており、ときにアルコールを飲みすぎて、息子をほったらかしにすることもしばしばあったらしい。それがアロンソ氏にとって大きな心の傷になっているという事実が、その後の彼の箱庭を読み解くうえでの鍵となってくる。
そしてアロンソ氏は、だいぶ後になって「日本のキツネ」が出てくる作品をつくる。箱庭の中心にテーブルと三脚の椅子、左下に空のベビーベッド、右上には網膜にドクロが映った眼のイラスト(だまし絵で有名なエッシャーのイラスト)、そして左上に、日本好きのアロンソ氏が日本旅行で買ってきたキツネとタヌキの置き物が配置されている。パヴォーニは説明する。キツネは神的存在で、危険でもある一方で、人間を守り、また恩恵を与えてくれる。ポイントは、最初の作品で両親の人形が置かれていたポジションにこの両義的な存在が置かれているということだ。以降このキツネとタヌキは度々アロンソ氏の箱庭に登場する。決定的なのが砂で波をつくり、箱の右上に一本の木、その傍にキツネとタヌキを配置した「枯山水」風の箱庭だ。これは今までのアロンソ氏の箱庭にはなかったタイプの作品だ。アロンソ氏にとって日本は心を健やかにする、束の間の美の象徴なのだとパヴォーニは指摘する。これを機に、アロンソ氏の箱庭に自分の心の痛みを乗り越えて行こうとする兆候が見られるようになる。
素人ながらに本書を読了した私が思ったところが二つある。一つ目はキツネとタヌキの異物感だ。掲載されている写真からは明確には認識できないが、アロンソ氏が日本旅行で買ってきたキツネとタヌキは、観光地のお土産屋さんにあるような、かわいくデフォルメされたおもちゃのようだ。U字磁石、天使、エッシャーの眼など、箱庭を構成する他の置き物は、いかにも心理療法の記号として用いられて然るべきものという印象を受けたが、それらと比べてお土産のキツネとタヌキは、「同じ箱庭に並べていいの?」と疑いたくなる異物感があった。
もう一つは もしかするとアロンソ氏の個人的な性格かもしれないが、彼の箱庭における表現がとても「雄弁」だったこと。最相葉月の『セラピスト』を通して知った日本の箱庭療法は、もっと抽象的で、クライエントの表現も控えめだったように思う。これは日本に「箱庭療法」を取り入れた河合隼雄が、カウンセラーはクライエントの箱庭を受け止めるべきだが、早急に解釈しすぎないという手法の表れかもしれない。
そんな河合の解釈とは違い、アロンソ氏の箱庭では重要なファクターであるキツネとタヌキに、あっさりと意味を与えすぎている気がした。イタリアでは西洋においてエキゾチックに見える対象物を精査せずに受け入れる傾向があるように思う。漫画やアニメ、武士道や仏教文化もそうだ。イタリアと日本で言語的に隔たりのある箱庭療法でも、その傾向には変わりがなかった。もちろん、数あるクライエントのうちの一つのケースにすぎないし、エキゾチックなものを受け入れること自体が悪いわけではない。ただもう少し慎重になってもいいのではないかと、『アロンソ氏と日本のキツネ』を読んで改めて感じた。
二宮大輔(翻訳家・通訳案内士)
2012年ローマ第三大学文学部を卒業。観光ガイドの傍ら、翻訳、映画評論などに従事。訳書にガブリエッラ・ポーリ+ジョルジョ・カルカーニョ『プリモ・レーヴィ 失われた声の残響』(水声社)、クラウディオ・マグリス『ミクロコスミ』(共和国)など。