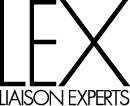詩と詞の違いは……?
2025.02.14
「日本語は自分の舌を使って発音する快楽をなくしてしまった」
雑誌「ユリイカ」の1973年3月号で、谷川俊太郎が言語学者の外山滋比古と対談したときの発言だ。ミュージシャンとしても活動する私は、似ているようで違う「詩」と「歌詞」はどのような関係にあるのか個人的に気になって、いろいろ本を読んでいくうちに、50年前の「ユリイカ」に掲載されている「詩的言語へ 日本語のリズムと音」という特集にたどりついたのだった。対談で言われているのは、日本語の詩は書き言葉に特化していて、実際に言葉を口に出すことを想定していない云々。この言説は何やら詩と詞の違いを理解するうえで大事そうだ。というわけで、これを主題に改めて考えを巡らせてみようと思う。
15年ほど前、イタリアに留学していたころに、ローマ大学の日本語学科の友人が卒業論文を書くということで、その手伝いを頼まれた。卒論のテーマは「日本語に訳されたカンツォーネ」。ここでいうカンツォーネは60年代、70年代に流行ったいわゆるイタリアのポップス歌謡のことで、日本でもヒットして日本語に訳されて歌われた曲がいくつもある。私と友人が日本語の訳詞を調べて発見した法則は、メロディーを重視して訳詞をつくる場合、本来の歌詞の意味を保つことが難しいというものだった。例えば、カンツォーネ黄金期に活躍した歌手ジリオラ・チンクエッティが歌った“Napoli fortuna mia”という曲がある。
Napoli, fortuna mia, (ナポリ 私の幸せ)
m’ero scurdate che a felicità(私は忘れていなかった 幸福は)
è ‘n ‘a nuttate e stelle,(星が見える深夜)
terra ‘e Santa Lucia,(サンタルチアの地)
è ‘na canzona antica(いにしえの歌)
cantata m’iezz’ a’ via.(通りで歌われている)
これを同時代の日本人歌手の伊東ゆかりが日本語訳でカバーしているのだが、その歌詞が以下になる。
ナポリ夢の町
幸せにあふれて
星降る夜の
サンタルチアよ
街に流れる
懐かしの歌

一行目ではfortuna mia(私の幸せ)が日本語訳では消え去り、代わりに「夢の町」という創作ワードが出てくる。二行目以降は原語の意味を可能なかぎり踏襲しつつ、メロディーに合う日本語訳をあてている。ここで次なる問題が浮上する。韻が踏めていない。”fortuna mia” “Santa Lucia” “m’iezz’ a’ via”といふうに-iaの母音で韻を踏んでいるのが原曲の特徴なのだが、それが日本語訳では再現できていない。とは言っても、上述のイタリア語の歌詞に併記した日本語訳を見てもらってもわかるように、直訳した場合は、韻はおろか言葉をメロディにのせることさえも困難なのだ。外国語の歌詞を日本語に変換する作業は翻訳ではなくいわば脚色と考えたほうがよさそうだ。それを念頭に置いたうえでの妥協点が、「夢の町」の出現なのだろう。ゆえに友人の卒業論文の結論は「優れたメロディーと優れた訳詞は両立しえない」。ところがそれを両立させる奇跡の曲が存在する。ディズニー映画『アナと雪の女王』の“Let it go”である。
これに関しては原曲の英語、日本語訳詞とイタリア語訳詞の3バージョンを比較しつつ話を進めたい。まず世界的に有名な英語の歌詞はこうだ。
Let it go, let it go(そのままに そのままに)
Can’t hold it back anymore(もう抑えられない)
そして松たか子が歌った日本語版の歌詞がこちら。
ありのままの
姿見せるのよ
ほぼ原語の意味をキープしつつ、Let it goの-oの韻を「ありのままの」で一致させている。それに続く行も-oの母音で韻を踏んでいる。これはすごい。ちなみに訳詞を担当したのは劇作家で翻訳家の高橋知伽江。劇団四季のミュージカルなどで翻訳を担当しているその道のエキスパートだそうだ。
次にイタリア語バージョンを見てみよう。
D’ora in poi lascerò(これから そのままにする)
che il cuore mi guidi un po’(心が導くままに)
なんとこちらも意味をキープさせつつ末尾は“D’ora in poi lascerò”と-oで韻を踏んでいる。日本語訳だけではなく、イタリア語訳でも意味とメロディーを両立させている。これはもしやと思い、他の言語で歌われた“Let it go”の同じ箇所をチェックしてみたところ、ドイツ語→〇、スペイン語→△、フランス語→×という結果がわかった。言語によってはこの離れ業をするには限界があるのだろう。他言語と比べても秀逸なイタリア語の訳詞を担当したのはロレーナ・ブランクッチ。この人もイタリアのアニメ吹き替え界のエキスパートらしい。そんな彼女が『アナと雪の女王』の本国公開から間もない2014年1月のインタビューで訳詞の極意を話してくれている。曰く、ディズニー映画は歌が物語のキーになることが多く、子供が字幕を完全に追いきれないことを想定すると、優れた吹き替えが必須となる。そして歌のシーンでは、通常の会話シーンよりもくちびるの動きが遅いため、リップシンクが重要になってくる。
リップシンクとは、吹き替えにおいてキャラクターの口の動きと吹き替えの台詞がシンクロしていることである。なるほど、特に“Let it go”からもわかるように、各節の歌い終わりや音を伸ばす箇所、アクセントをつける箇所は、映像で口の形がはっきりわかるため、原語と母音が一致した吹き替えが必要なのだ。私が無知で知らなかっただけだが『アナ雪』だけでなく、その他のディズニー映画でも、同様の理由でハードルの高い音韻の一致が求められているようだ。
ここで冒頭の「ユリイカ」の話に戻る。歌詞とは、より具体的に口に出す想定のもとに創作される詩の一形態だと言えるのではないか。それがディズニーの訳詞のように、場合によってはより高次の制限のもとに創作される。制限がある分、言葉の自由度は低くなるが、「自分の舌を使って発音する快楽」は非常に大きいように思う。
だが、ここで妄想が働く。AI技術が発達すれば、アニメーションにおいても各言語に合わせた口の動きの再現が可能になり、“Let it go”的な訳詞の必要性はなくなるのではないか。もしかしたら、訳詞という言葉の快楽は絶滅の危機に追いやられ始めているのかもしれない。
二宮大輔(翻訳家・通訳案内士)
2012年ローマ第三大学文学部を卒業。観光ガイドの傍ら、翻訳、映画評論などに従事。訳書にガブリエッラ・ポーリ+ジョルジョ・カルカーニョ『プリモ・レーヴィ 失われた声の残響』(水声社)、クラウディオ・マグリス『ミクロコスミ』(共和国)、『ぼくがエイリアンだったころ』(ことばのたび社)など。